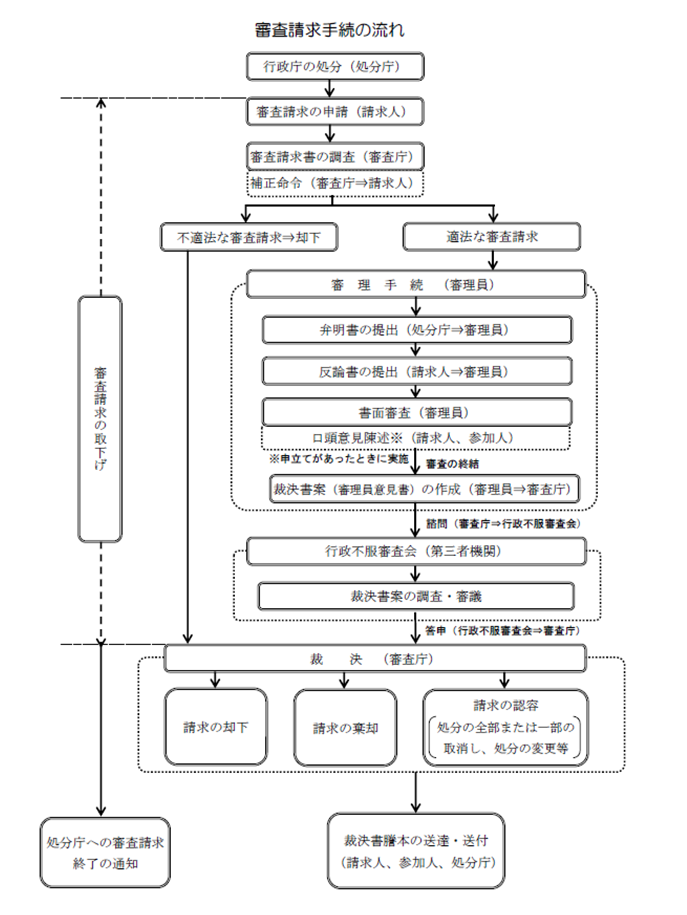行政法 > §30 行政不服審査法の手続
1.書面提出主義
他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。
・口頭による審査請求は、審査庁に対して行うのみならず、処分庁等を経由する場合も考えられるので、陳述を受けた行政庁との文言になっている。
・口頭による審査請求は、審査庁に対して行うのみならず、処分庁等を経由する場合も考えられるので、陳述を受けた行政庁との文言になっている。
2.誤った教示の救済
〇教示=処分庁が処分の相手方に対して、当該処分について不服申立てをすることができる旨、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てをすることができる期間など、不服申立てに関する手続を示す制度
〇審査請求をすべきでない行政庁を教示した場合→審査請求書の提出を受けた行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
〇再調査の請求ができないのに、できる旨の教示
再調査の請求を選択することはできず、審査請求以外の選択肢はないので、処分庁は、速やかに、再調査の請求書等を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつその旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
〇審査請求をすべきでない行政庁を教示した場合→審査請求書の提出を受けた行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
〇再調査の請求ができないのに、できる旨の教示
再調査の請求を選択することはできず、審査請求以外の選択肢はないので、処分庁は、速やかに、再調査の請求書等を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつその旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
3.補正と却下裁決
審査請求書の記載に不備がある場合、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
審査請求人が期間内に不備を補正しない場合→審査庁は審理手続を経ないで、裁決で当該審査請求を却下できる。
また、審査請求が「不適法であって補正することができないことが明らかなとき」も同じである。この例としては、審査請求の年月日から審査請求期間を徒過していることが明らかで、徒過につき正当理由がないことが明らかな場合など。
審査請求人が期間内に不備を補正しない場合→審査庁は審理手続を経ないで、裁決で当該審査請求を却下できる。
また、審査請求が「不適法であって補正することができないことが明らかなとき」も同じである。この例としては、審査請求の年月日から審査請求期間を徒過していることが明らかで、徒過につき正当理由がないことが明らかな場合など。
4.執行停止
〇原則は、執行不停止である。審査請求がなされたからといって、行政の執行が停止されるわけではない。仮にこれを認めると、とりあえず審査請求をし、時間稼ぎをしようとするケースが増え、行政の円滑な運営が阻害され、公益が損なわれるおそれがあるからだ。
〇しかし、例外的に、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置」を採ることができる。
*執行停止は処分の効力に関わるものであるから、執行停止の判断権限は審理員ではなく審査庁にある。
〇行政事件訴訟法上の執行停止と異なり、職権による執行停止も認められている。
その他の措置とは、原処分に代わる仮の処分をいう。
〇しかし、例外的に、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置」を採ることができる。
*執行停止は処分の効力に関わるものであるから、執行停止の判断権限は審理員ではなく審査庁にある。
〇行政事件訴訟法上の執行停止と異なり、職権による執行停止も認められている。
その他の措置とは、原処分に代わる仮の処分をいう。
5.義務的執行停止
1.審査請求人の執行停止の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認められるときは、審査庁は執行停止をしなければならない。
ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りではない。
ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りではない。
6.執行停止の取消し
執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかになったとき、審査庁は職権で執行停止を取消すことができる。
行政事件訴訟法の執行停止では、裁判所は職権で執行停止の取消しをすることはできない。
行政事件訴訟法の執行停止では、裁判所は職権で執行停止の取消しをすることはできない。
7.審査請求の取下げ
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取下げることができる。取下げは書面でしなければならない。